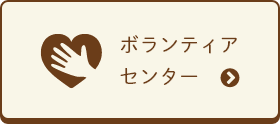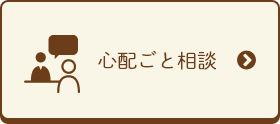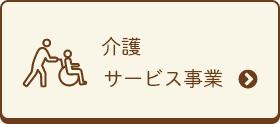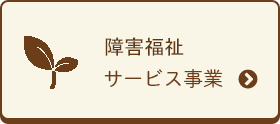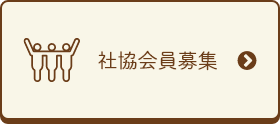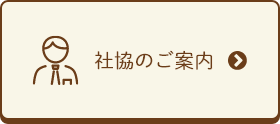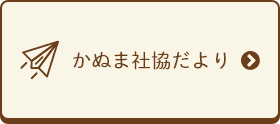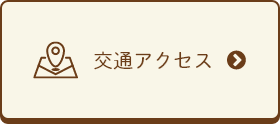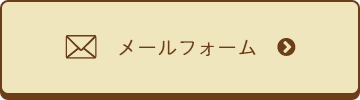鹿沼市千寿荘 非常勤職員(支援員)の募集について
鹿沼市社会福祉協議会
鹿沼市千寿荘 非常勤職員(支援員)の募集について
1 職種及び予定人員 支援員(非常勤) 1名
2 雇用期間 採用日から令和7年3月31日まで(契約更新の可能性あり)
3 勤務地 養護老人ホーム千寿荘(鹿沼市日吉町386番地)
4 勤務時間 午前9時00分から午後4時00分 週2日程度
5 業務内容 利用者への生活支援(入浴支援も含む)業務等
6 給与等 時給 1,010円
※ その他、臨時職員・非常勤職員の雇用に関する要綱に基づき支給
7 受験資格 特に資格は問いませんが、介護福祉士、介護職員初任者研修等の介護資格があると尚可。
8 応募手続 下記の書類を募集受付期間内に鹿沼市社会福祉協議会(鹿沼市万町931-1)へ持参
または郵送にてご提出ください。
① 市販の履歴書(写真添付) 1部
② 職務経歴書 1部
③ 資格証明書の写し(有資格者) 1部
9 募集受付期間 採用者が決定するまで
10 募集受付時間 午前8時30分から午後5時まで
11 試験等 面接試験 ※随時実施予定
<連絡先>
鹿沼市社会福祉協議会 住所:鹿沼市万町931番地1
鹿沼市総合福祉センター内
電話:0289-65-5191
担当:地域協働課 企画経営係 福田
社協のお仕事紹介(^^♪
※詳細は下記の動画をご覧くださいm(__)m
職員紹介・休日の過ごし方(^^♪
※詳細は下記の動画をご覧くださいm(__)m
News
お知らせ
お知らせ
2024-03-19
第20回ふれあいフェスタinかぬま開催注目オススメ
2024-03-19
ひきこもりフォーラムinかぬま開催注目オススメNEW
2024-03-18
新小学1年生へ黄色い帽子の贈呈!注目チェック
2024-02-01
2024-01-24
『令和6年能登半島地震』街頭募金を実施しました。注目チェックNEW
| もっと見る |
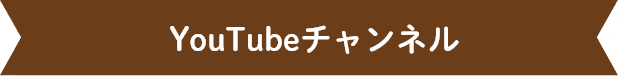
鹿沼市社会福祉協議会
CAMP CAMP ちゃんねる【鹿沼社協】